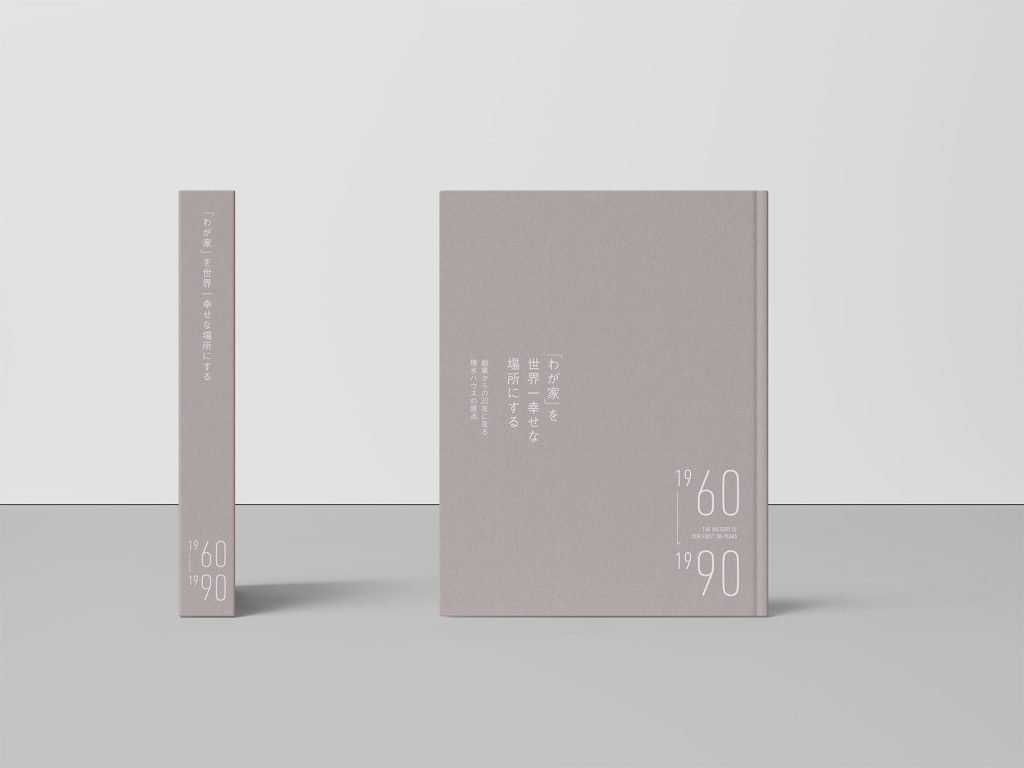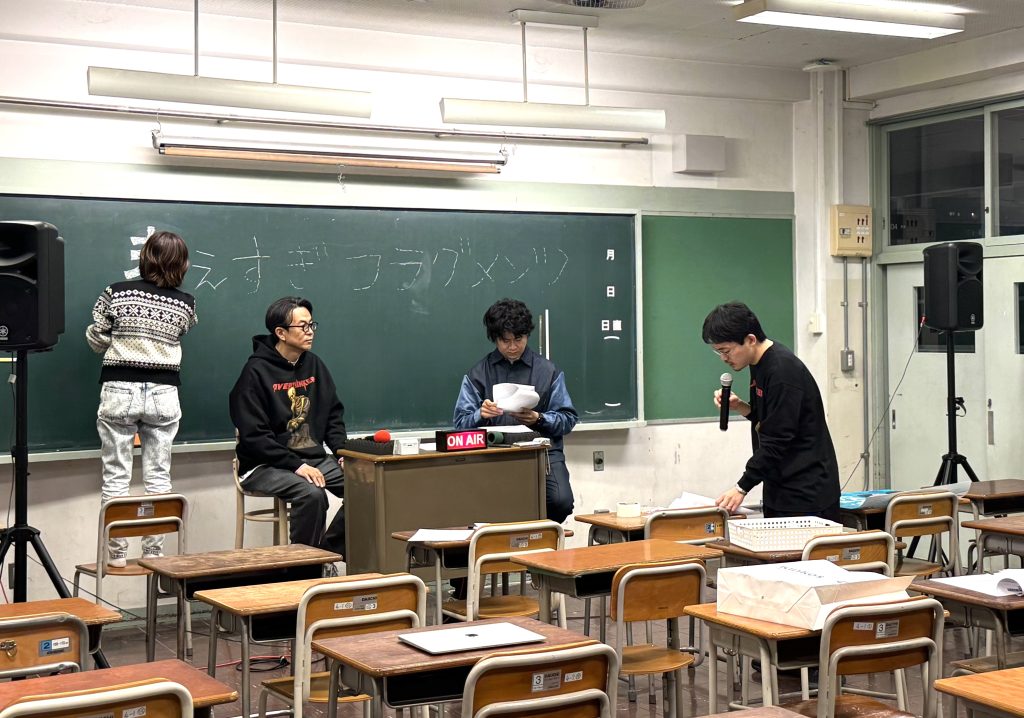企業のブランディングやマーケティングに携わる方から寄せられたお悩みに、クラシコムの代表取締役社長・青木耕平が「こうかな?」「こうかも!」とうろうろ思考を巡らせながら、お答えする企画の第二回。今回は、D2CブランドでSNSを担当している方から寄せられたこんなお悩みです。
「マーケティング担当として、自社のSNS運用を続けているものの思うような成果(売上)が見えず、悩んでいます。SNSアカウントのKPIをどのように設定すれば良いでしょうか? またアカウントの運用をやめる、アクセルを踏むタイミングをどうやって判断していますか? すぐに結果が出るものではないとも感じていて、長期的にブランド価値を高め、ファンとの関係を築く場として重要な役割を果たすと思うのですが……」
*記事の最後に、青木へのお悩み募集フォームのご案内がありますので、ぜひご記入ください。

Q.SNS運用のKPIはどう設定する?

クラシコムのSNSはKPIを設定していません。これは「数字を見ない」のではなく「絶対値を目指さない」ということ。山の頂きを見ながら歩くのではなく、どこに辿り着くかはわからないけれども足元を見ながら歩いているような状態です。
私たちがSNSで大切にしていることは、お客さまにとって良いコンテンツか、ビジネスとして合理性があるか、やりかたが真っ当であるかどうか。お客さまが喜ぶことを私たちからお届けして、好きになってもらい、結果としてエンゲージメントが生まれる状態を理想としています。たとえばInstagramで商品を多く紹介しているのは、売りたいからというよりも、お客さまが喜んでくださるからです。
また、すべての課題をSNSだけで解決するのは難しいからこそ、SNSをどの場面でどう使うかが重要だと考えています。認知から購入、リテンションとある中で、それぞれの間が開きすぎないよう、丁寧にラダー(梯子)をかけるように考えています。
クラシコムでは、SNSを主に認知のフェーズに使っていて、見込み客が私たちを知っている状態、あわよくばちょっと好きかもしれないという状態を目指しています。そこに適切な接点(広告)を設けることで、コンパクトなCPAで広告を継続できますし、ぐるっとまわってSNSが再来訪を促すためのラダーにもなる……というサイクルができています。
Q.運用をやめるタイミングは?

クラシコムには、SNSの専任グループも専任担当もありません。商品管理を担うMDチームが「北欧、暮らしの道具店」のInstagram運用を担当するように、その分野の仕事の解像度が高いスタッフが最適だと考えているので、どのSNSも兼任で運用しています。また、それぞれの知見を共有するために、クラシコムでは各SNS担当者が集まる定例会議を行っていて、まるで研究発表のように試行錯誤をシェアしています。同じやりかたを続けるだけでは成長するのが難しいSNSだからこそ、気づきや発見を担当者同士で共有し合い、それぞれの場所で活かすための「インプットの機会」が必要だと考えているからです。
こうした体制によって小さなコストで運用できているので、SNS運用を休むことはありますが、撤退の判断はしません。撤退を選ばないのは、小さくても運用を続けていれば急に追い風が吹いたときに風を受けられる可能性があるからです。風が吹かないからといって帆の手入れをしないでいると、いざというときに動けません。
ただし「小さく続ける」のは「怠けて良い」ということではなく、割り当てられたリソースと環境下で最善を尽くし続けるということです。風が吹いた時にどう受けるか、常に脳に汗をかきながらアップデートしつづける姿勢を担当者に希望しています。ですから、もし完全に撤退するとしたら、担当者全員が希望を持てなくなったときでしょう。SNSは担当者がモチベーションを失ってまで、必死になってやるものではないと思います。
Q.アクセルを踏むタイミングは?

SNS運用のアクセルを踏むタイミングは明確です。小さくいろいろ試しているうちに予期せぬ成功のシグナルをキャッチして「この方程式ならいけるね」と確信を持てたら、惜しみなくリソースを投入します。これはSNS以外においても同様です。タイミングによっては、世間から見た時、ものすごく大きな勝負をしているように見えるようなこともあります。
なぜこんなやり方ができるかというと、先のことを予想したり期待したりしていないからです。「こうなるはず」と期待を持って大きく試してうまくいかなかったら撤退……ではなく、予想をせず、まずは小さく試す姿勢を貫いています。ほぼコストがかからない状態でやってみて、明確に因果関係が分かる状態になったとき、思い切りアクセルを踏む。なのでもし今からSNSを新しく始めるなら、できることは全部やります。やらないチャネルはないけれども、全て小さく始めますね。
連載「クラシコムのうろうろマーケ談話室」
1:Q.ブランディングの費用対効果が見えず、不安です
2:Q.SNSのKPIはどう設定する?運用をやめるとき、アクセルを踏むときの判断は?
関連記事
Instagram
・フォロワー127万人「北欧、暮らしの道具店」のInstagram運用 9年間のあゆみ1分間で何を伝えられるだろう? インスタグラム「リール」チームに密着しました
・お店とお客さまの「今」を繋ぐ。インスタグラムチームに密着しました
YouTube
・過度にドラマティックな編集はしない、「北欧、暮らしの道具店」のドキュメンタリー5つの特徴
・公式YouTubeチャンネル登録者数60万人、総再生回数1億5000万回、総再生時間1000万時間突破