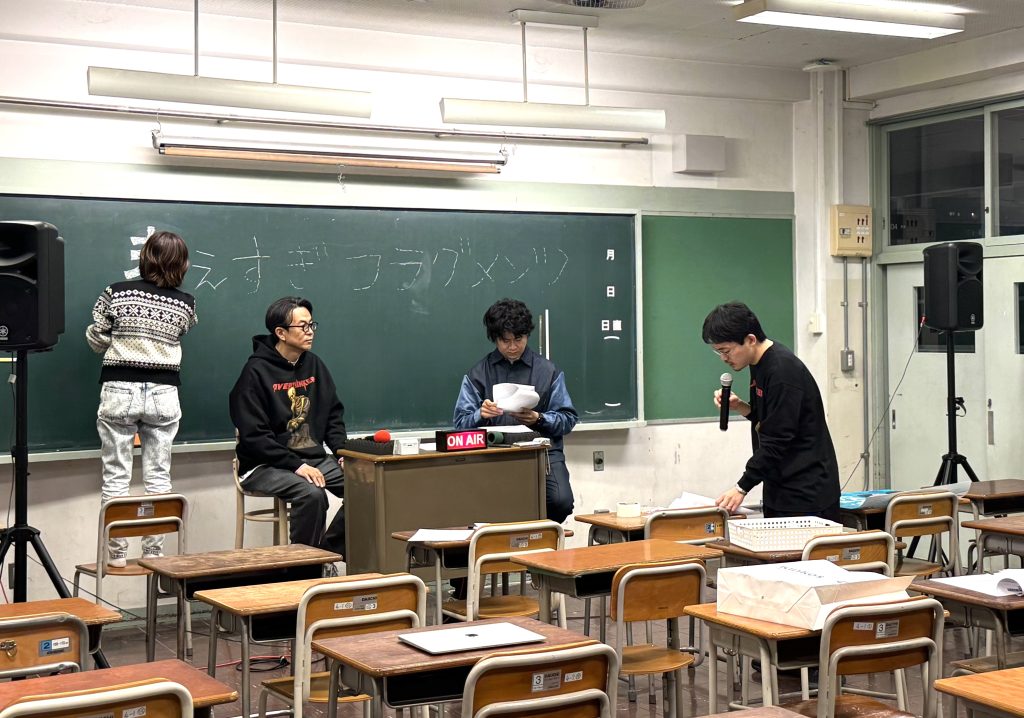クラシコムの仕事の裏側や大切にしている考え方などをお伝えしている「北欧、暮らしの道具店の裏側」。今回は、当店のスタッフが登場する読みものについて、お届けします。
当店の読みものコーナーでは、「クラシコムのしごと」や「スタッフインタビュー」など、スタッフが登場する記事を数多く公開しています。これまでの企画の変遷と編集の意図について、メディア編集グループのマネージャー・齋藤に、聞いてみました。
写真:メディア編集グループのマネージャー・齋藤 (撮影:川村恵理)
「私たち」を感じられる場所になるために

–– 「北欧、暮らしの道具店」の読みものは、スタッフが多く登場します。
「北欧、暮らしの道具店」は、私たちみたいな誰かが、フィットする暮らしをつくることを助ける場所でありたい。この場所で、読者と一緒に、ユニークな視点や新しい選択肢をみつけたい、という思いで読みものをつくっています。だからこそ、私たちがどんな人で、どんな人たちがつくっているお店なのかを、日々訪れるお客さまに知っていただくことが重要です。
スタッフが読みものに登場する理由は、一人ひとりがクラシコムでどんなことを考えて働いているのか、何をお客さまに届けたいと思っているのか、アイテムのリアルな使い心地はどんな感じなのかなど、私たちの声を届けたいという思いから。
スタッフが登場する読みものに触れていただくことで「なんだか自分みたいな人たちが、ここにはいるんだな」と安心感や信頼が時間を経て生まれ、それが居心地の良さや、お店を再訪するきっかけにつながっていくのかなと思っています。

–– スタッフが登場する読みものは常に更新されている一方、「スタッフコラム」のようにそれぞれの主観でいまの気持ちを綴る読みものは、少なくなってきたように感じます。
あるタイミングで店長の佐藤から「よりサステナブルな場所を目指すためにも、お客さまもスタッフもみんなが“私たち”を感じられるような読みものを、充実させていくほうがよいかもしれないね」と気づきが共有され、そこから少しずつコラムの数を減らし、メディア全体でスタッフ一人ひとりの個人性から「私たち」を感じるような方針へシフトしていきました。
今後もある程度の粒度を保ちながら、スタッフの個人性については、そのときどきの状況や方針にあわせて検討していきたいと考えています。
新しいスタッフの一面を、信頼のきっかけに

–– 2021年末には新企画「クラシコムのしごと」が始まりました。
当時は、映画『青葉家のテーブル』の公開があり、YouTubeを含め、あらゆる方向から訪れるお客さまが増えて、社内でも働くスタッフやチームが増えてきた頃でした。そんななか、私たちがどんな人たちなのか、お客さまに対して日々どんな気持ちで向き合っているのか、あらためて伝える場所をつくりたいという思いで企画したのが「クラシコムのしごと」でした。
「クラシコムのしごと」はひとりのスタッフではなく、チームやプロジェクトの取材を通して私たちの仕事観をお伝えする特集です。2021年秋頃まではカジュアルに現場の空気をお届けする「今日のクラシコム」を更新していましたが、「クラシコムのしごと」では、私たちが仕事に向き合う姿勢を、まっすぐに伝えることを目指しました。

–– 2022年には「スタッフインタビュー」も始まりました。
こちらは2名のスタッフによるスイッチインタビューです。お店とスタッフの新たな一面をお届けするために「変わらないために変わり続けること」をサブテーマに掲げた特集でもあります。
クラシコムに入ってからの話はもちろんですが、このインタビューでは、「入社前」の葛藤や悩みもじっくり聞いているのがポイントです。スタッフが、どんな葛藤を経てここまでの道のりを歩んできたかを聞いています。
お客さまの年齢層の幅も広がるなかで、もしかしたら、入社前の20代前半の葛藤に共感してくださる方もいるかもしれない。これまでお伝えできていなかった角度から見えるスタッフの姿も、この企画でお届けしたい「新たな一面」でした。
「クラシコムのしごと」「スタッフインタビュー」どちらの企画も「この人たちがつくる場所だから信頼してみようかな」」「大事なタイミングで買い物するならここにしよう」とお客さまが当店を身近に感じられるきっかけになれば嬉しいなという思いで、更新を続けています。
お客さまもスタッフも、ひとりの生活者である

–– 「スタッフコラム」のように更新のかたちを変えてきた企画がある一方、スタッフが登場する読みもので長く続く企画もありますね。
2008年頃にスタートした「スタッフの愛用品」は、スタッフが実際に暮らしながら愛用するなかで感じたリアルな声が詰まっている読みもので人気コンテンツのひとつです。他にも2015年から続いている「スタッフ着用レビュー」は現在も更新していますし、「スタッフのお買い物」「台所でおつかれさま」といった当店のスタッフを取材対象とした暮らしやインテリアを紹介するコーナーもあります。
こうしたコンテンツのおかげで、お客さまが当店に訪れたとき、スタッフの存在を全く感じられないということはなく、常に読みものを通して「私たち」の温度感を感じられる状態になっていると思います。
–– スタッフが登場する読みものを編集するとき、特に気をつけているポイントは?
スタッフが登場する読みものかどうか、お客さまは区別して読むわけではないので、編集方針はどの記事も変わらず、スタッフもお客さまもひとりの生活者であり「フラットな関係」であるかどうかに気をつけています。
例えば、執筆担当のスタッフが他のスタッフを取材するとき、つい持ち上げてしまっていないか。商品の開発秘話などは、内輪な空気にならないよう、お客さまだったらどんなことが気になるかな? と俯瞰して編集するよう心がけています。
「私が書きたいもの」ではなく「私が読みたいもの」を書く

–– 「フラットな関係」について、もう少し詳しく教えてください。
読みものではありますが、当店に訪れた方には「ここで耳にする言葉はどれも心地よいな」「自分と同じ人たちが集まっている場所だな」と感じていただきたいと願っています。だからこそ、スタッフ間はもちろん、お客さまとフラットな関係を築くこと、お客さまと一緒に考えるという立ち位置は、読みもの全体において、とても重視しています。
企画については「お客さまが読みたそうなもの」「私が書きたいもの」ではなく「私が読みたいもの」を書くという姿勢を一貫しています。また、お客さまにへりくだりすぎても、逆に「これがよいです」「こうしましょう」と押し付けたりするのも、心地よい場所と感じられないと思うので、あくまでお客さまと一緒にユニークな視点や新しい選択肢をみつけていきたい、という立ち位置で編集します。
さまざまなライフスタイルの方が読んでくださるので、特定のカテゴリを批判していないか、誰かを傷つける表現になっていないかも重要です。ささやかな言葉や表現ひとつで、居心地の良さにつながるし、一方で違和感にもなり得るものだと思うので、伝え方は特に意識しています。
「今日この場所に来られてよかった」と思っていただけたなら

–– 「北欧、暮らしの道具店」の読みものを通じて、あらためてお客さまとどんな関係を築いていきたいか、教えてください。
読みものの本数を重ねていく中で、お客さまとの接点も、少しずつ増えているような感覚があります。2024年3月、小原晩さんの連載エッセーをスタートしたところ、20代のお客さまから感想メールをいただく機会が増えました。感想を送るというのは、とてもとてもエネルギーのいること。あぁこんな年齢層の方たちも読んでくださっているのかと、新しいパワーを感じました。
2カ月に一度を目安に更新しているスタッフインタビューも、公開するたびに、社会人になりたての方や仕事復帰をするタイミングの方、今はお仕事から離れているけれども昔を思い出して嬉しくなり感想を送ってくださった方……とさまざまな立場・年齢の方からご感想をいただくことが増えました。
スタッフが当店のアイテムの開発秘話を聞く特集にも、同じように悩みを抱えていたお客さまから、アイテムへの共感の声や、真摯な要望をいただくことが、以前よりも増えたように思います。
これからも、当店の読みものに触れていただくことで、明日は今日よりいい日になりそうだなと希望を持てたり、自分の今の暮らしや歳を重ねることに対してポジティブな感情を持つきっかけが生まれたり。「今日この場所に来られてよかった」「また明日も訪れたいな」「私のための場所だな」そんなふうに感じていただけたら嬉しいです。