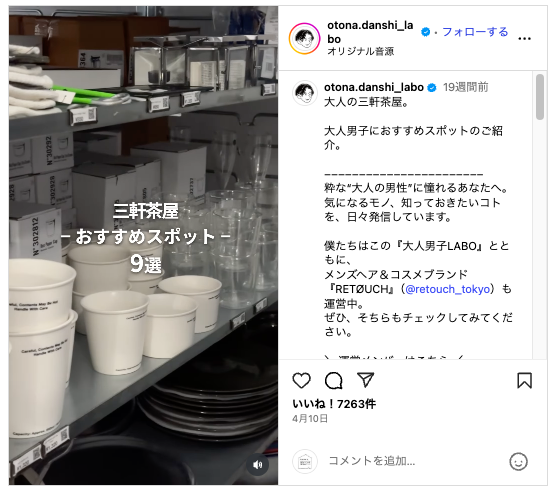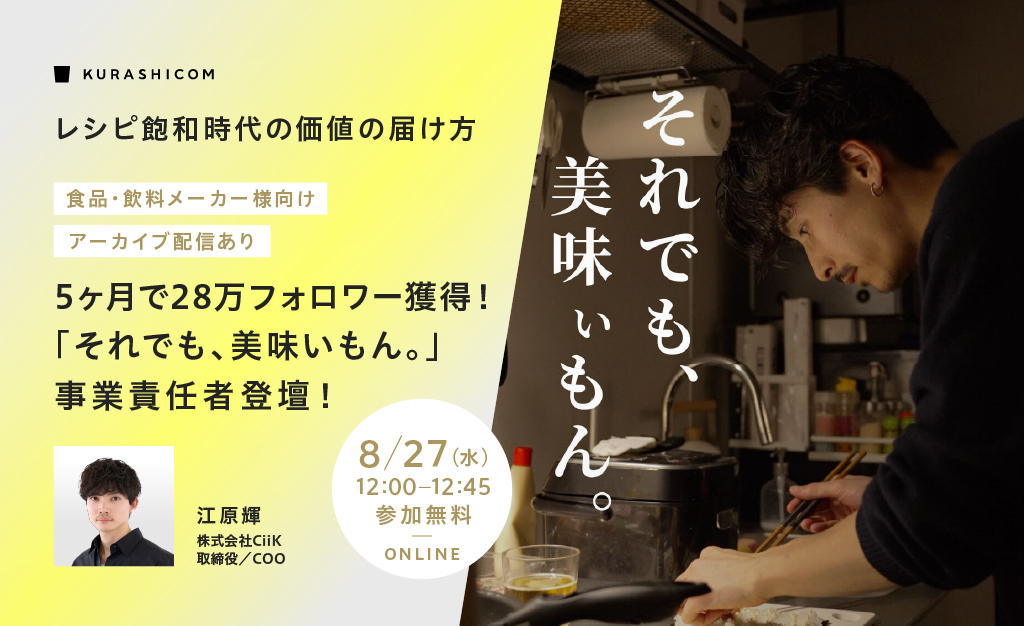株式会社クラシコムのブランドソリューショングループが主催し、企業のマーケティングやプロモーションを担当されている方々を対象に開催しているイベント「BRAND SOLUTION SALON」。
この度、クラシコムブランドソリューショングループは、コンテンツ・商品開発・リアル店舗運営を掛け合わせた独自のマーケティングを強みに事業を成長させている、注目のライフスタイルカンパニー・株式会社CiiKが運営するInstagramアカウント「それでも、美味いもん。」の専属エージェンシーとして期間限定で協業していくことになりました。
6月26日に開催された第10回は、ゲストに株式会社CiiK代表取締役の宮永えいとさんをお招きし、クラシコム代表・青木耕平と共に「事業を成長させるSNSマーケティングとは?」をテーマにトークセッションを行いました。約30ブランドの担当者様にもご参加いただいた当日の様子を、ぜひご覧ください。

▲株式会社CiiKの宮永えいとさん

▲クラシコム代表 青木耕平

▲モデレーターを務めるのはクラシコム ブランドソリューショングループの高山達哉
目次
・CiiKとクラシコムの共通点とは?
・コンテンツは商品開発部。CiiKが語るSNSの役割と機能
・SNSにKPIは不要?成果と検証の向き合い方
・「商品を勧める=相手に嫌われる」という思い込みに囚われがち
・属人性と有益性は1:1
・良いコンテンツが広告効果を高める
・SNSにおける属人性と再現性
・参加者からの質問タイム
CiiKとクラシコムの共通点とは?

―CiiKが運営するInstagramアカウント「それでも、美味いもん。(以下、それうま)」とクラシコムがエージェンシー契約を結ぶことになりまして、これからさまざまな取り組みをご一緒していく予定です。まずクラシコムとCiiKの出会いからお話できればと思います。
青木:僕は今52歳なんですけど、コロナ禍で老いを感じるようになりまして……。スキンケアやヘアケア、年齢相応のおしゃれとか、そういう悩みを感じているときに出会ったのが「大人男子ラボ」のYouTubeでした。そこで言われるがままにヘアケア商品を買ったり、ドライヤーの使い方を変えてみたり…と、すごく影響を受けたんですよね。
「北欧、暮らしの道具店」は、女性のお客様が多いメディアですが、どういうふうにしたら男性向けのライフスタイルメディアは成立するのだろうか?というのは、これまでも考えていて。なかなか思いつかずにいたのですが、「大人男子ラボ」を見て、「これだ!」と思いました。その後、ご縁があって実際にお会いし、交流が始まりました。
「それでも、美味いもん。」とのタイアップに関する
お問い合わせはこちら

―改めて株式会社CiiKについて教えていただいてもよいでしょうか?
宮永:「大人男子ラボ」は、「身だしなみの文化をつくる」というミッションを掲げ、3つの事業を展開しています。1つ目は美容室。私はもともと美容師で、15年くらいハサミを使って人生を変えるお手伝いをしてきました。リアルな場で深いコミュニケーションをしているうちにもっと多くの人に自分の知識を広げたいと考えるようになり、「大人男子ラボ」というメディアを立ち上げコンテンツ配信を始めました。YouTubeとInstagramを中心に身だしなみ回りの情報を発信しています。
メディアを始めたことでいろいろな方と出会うことができ、そこから様々な課題に気づけたので、それを解決するための道具をつくろうということで「RETØUCH」というヘアワックスやスキンケアのブランドもスタートしました。
メディアの読者から、毎日DMやコメントで課題やお悩みをいただくので、それを解決するプロダクトをつくって、またコンテンツに載せて届けるというサイクルを回しています。
―今回、クラシコムとご一緒させていただくことになった「それでも、美味いもん。」は、「大人男子ラボ」からスピンオフしたアカウントなんですよね?
宮永:もともとは「大人男子ラボ」の一企画としてやっていました。自己投資意欲の高い男性が仕事終わりに、ご飯をつくって食べるという動画です。焼きそばをつくってキッチンで食べる動画が170万再生を超えるなど、数字を伸ばしたことで手応えを感じ、独立アカウントとして展開することに決めました。
青木:ちなみにアカウントをつくってどれくらいでこの数字なんですか?(Instagram:20.5万フォロワー、tiktok:9.3万フォロワー/8月18日時点)
宮永: 立ち上げは2025年3月で、3カ月で13万人ぐらいまで伸びたので、我々も驚きました。それだけ需要があるんだなというふうに捉えていますね。
コンテンツを走らせていると、「こういうご飯が食べたい」「これは微妙」「これをつくったらパートナーに喜ばれた」みたいなコメントがどんどん届くようになるんですよね。届いた課題を解決することこそが我々の役割だと考え、コンテンツ制作に取り組んでいます。
ご一緒させていただくブランドさんの商品を取り入れながら料理をつくったり、商品開発をしたり、メディア発の課題解決には多様な可能性があると感じています。ちょうど今後の展開を加速させたいというタイミングで、クラシコムさんとご一緒することになりました。
青木:僕はバズる直前くらいに見ていて、「すごいよね」って話していたんですよ。すでに伸びる気配を感じていて、やはり実際にバズっていて。それぐらい秀逸な企画だと思いました。
定型フォーマットの中にさまざまな要素を組み込めるのが良い点ですよね。コンビニで売っているものをアレンジしたり、食べ物だけじゃなくて一緒に飲むビールとかジュースとかも扱えるだろうし、飲みすぎた翌日をテーマに薬もできそう。決まった型の中で交換できるからこそおもしろい。「これは絶対におもしろい。一緒に取り組みたい」と思い、こちらから声をかけさせていただきました。
―CiiKさんの事業とクラシコムの共通点はどんなところだと思いますか?
青木:我々もCiiKさんと同じように、強みは動画や記事などさまざまな形態のコンテンツです。そこからお付き合いがはじまったお客様にインテリア、雑貨、洋服、コスメなどのさまざまなものを買っていただいています。
我々の場合、テレビで紹介されたり、CMをきっかけに出会うこともありますが、メルマガやアプリ、Podcast、Instagram、YouTubeも非常に重要です。「北欧、暮らしの道具店」は、オウンドメディアとSNSあわせて約800万人のフォロワーがいまして、継続的にコンテンツを届けることで、各プラットフォームのディスカバー枠に掲載されることがあります。ディスカバーで出会った人の中に「こういうコンテンツを見続けたい」という動機が生まれ、フォローや登録につながる。エンゲージメントアカウントとして登録していただければ、我々からのコンテンツが毎日届くようになります。そのコンテンツが届く機会から購入につながる可能性があるということでもある。
通常、D2C企業ですと、購入のときに初めてコンテンツの配信先となる連絡先を獲得できますが、我々はまずコンテンツで出会って、そしてお付き合いのベースとなるエンゲージメントをいただいて、そこにコンテンツを送り続けることで購入につなげるという構造がある。魅力的なコンテンツをエンゲージメントアカウントに積み上げていくことが成長戦略の柱になっています。そのあたりの考え方はCiikさんと共通している部分なんじゃないかなと思いますね。
コンテンツは商品開発部。CiiKが語るSNSの役割と機能

―今日は3つのテーマを用意しています。1つ目が「両社におけるSNSの役割」。SNSといってもチャネルがいろいろありますが、どういう役割でやっているのかをお聞きできればと思います。
宮永:我々の会社には商品企画部がないので、新しい商品をつくるときは、まずメディアをつくるところからはじめます。たとえばInstagramであれば、ストーリーズで質問をもらったり、メッセージのやりとりができたり。ライブ配信もできれば、コメントもいただける。コミュニケーションの機能がたくさんついているので、正しくセグメントしたメディアさえつくれれば、ユーザーから課題や物欲、意見がほぼ毎日来る状態がつくれるんですよね。そこまでいけたら、あとはその中からユーザーさんに求められるものを商品化していきます。そういう意味でいうと、事業におけるSNSの役割は商品開発部署に近い感覚です。
―おもしろいですね。今、何名の社員が在籍しているんですか?
宮永:社員は11名ですね。そのうちのほとんどがコンテンツをつくっています。コンテンツを配信することで課題を収集する役割もありますが、メンズ向けのヘアケアアイテムやコスメというカテゴリーは、使い方が分からない人が多いんですよ。だからこそ自社の商品の使い方を発信することが攻略本のようになる。我々のSNSの役割は、課題を集めて発信し、いわば“攻略本”として情報を届けること。バズを狙うのではなく、ユーザーとの実質的な対話を重視しています。
青木:社員の多くがコンテンツ制作を担っている一方で、売上の大半が物販というのは、非常に興味深い構造ですよね。でも、メディアのマネタイズの在り方として、すごく現代的だと思っていて。例えば、最近は人気のYouTuberを擁する会社も、売上の大半はグッズ販売なんですよね。つまり、広告やコンテンツ販売ではなく、メディアのコンテンツでお客さんとつながって、物販を通じてマネタイズすることのスケーラビリティが近年あらためて注目されてきました。
いきなりものを売るのではなく、まず関係を構築してから物販というのも重要だと思っていて。たとえば、街中で知らない人から「お茶しませんか?」って言われたら、困るじゃないですか。でも僕が宮永さんに「お茶しませんか?」っていったら時間が合えばしてくれると思うんです。それは誘う前に関係値ができているから。今までの広告というのは、街中でいきなりたくさんの人に声をかけるみたいなやり方でしたが、誘う前に友達になろう、友達になるために楽しい情報を提供しようということにすぎない。そう考えると実は人間の常識の中ですごく普通のことだなって。
宮永:すごくわかりますね。僕らも結局、発信しているという感覚じゃないので。あくまでもコミュニケーションをとっているという感覚ですから。

SNSにKPIは不要?成果と検証の向き合い方
―SNSをやっていると、エンゲージメント数やフォロー数、リーチ数とかKPIがあるケースが多いと思います。それぞれSNSにKPIはあるんですか?
青木:「北欧、暮らしの道具店」は、SNSにKPIはありません。ただ、月に1度、SNS含めたあらゆるチャンネルの担当者が集まって自由研究発表をする時間があります。今月の数字はこうだったという報告だけではなく、前月に「来月はこういう実験をやります」といっていたものの実験結果と、次の実験の予告をするんです。
各チャネルにKPIという数字を持たせていない分、競争はないから、各チャネルでつくったデータやノウハウは全て共有される。YouTubeでやったショート動画をインスタでもやってみようという話がすぐ生まれる。横展開が早いんです。
「どうしてそんなことに気づいたの?」というような質問も生まれて。みんな数字を出そうっていうよりは、何かおもしろいことに気づこうという空気になっています。実験自体は何かしらの課題を潰すようなものが多いので、結果として数字にもつながるという良い流れができていますね。
宮永:KPIはうちもないですね。事業を伸ばしたいし、コンテンツも伸ばしたいですが、バズりたくはないんですよね。
―なんでバズりたくないんですか?
宮永:バズると悲しいこともたくさんあるじゃないですか(笑)。ターゲットとしているユーザーさんがいて、こういう人たちの課題を解決したい、この人たちの人生を幸せにしたいという思いでコンテンツをつくっていますが、バズってしまうとターゲットの外にいる人たちや真反対にいる人にも届くことになる。そうすると、ターゲットとしている人たちを少し茶化すような声も出てきてしまいます。
コメント欄を見た我々を信じてくれている人たちが傷つくし、発信者としても傷つきます。なので、あんまりバズってほしくはないという中で、絶妙なバランスを攻めていますね。
去年までアカウントの伸びがすごかったこともあり、日々傷ついていました。傷を負いながらも、「こういうものだから……」とサムライのように立ち向かっていたんですが、1回やめよう、と。今いるファンとより深いコミュニケーションを取ろうと方針を変えました。
―どんなふうに変えたんですか?
宮永:伸びるコンテンツをつくるのではなく、オフ会でいろんな人の話を聞いたり、1週間に1回ストーリーズでQ&Aをやって1対1の質問に丁寧に答えるようになりました。アクションを変えてみると、美容室の店頭に来てくださるお客さんも増えましたし、ラフにDMを送ってくれるお客様やシェアしてくれるお客様も増えました。
青木:伝えようではなく、聞こう、受け取ろうという姿勢はうちとも近いですね。SNSを通してコンテンツを日々配信しているので、僕らの何かしらのページに毎日1000万〜3000万人ぐらいの人が接している計算になります。過去にコンテンツを見て知っていて、ちょっと好きになっているという状態で、アプリのダウロード広告を出すとかなり安価にCPIを獲得できるんです。
SNSだけで売上を強化していくというのはけっこう難しいことで、むしろアンチパターンにいってしまうことさえあると思っているので、KPIを追いはしないけれど、広告のCPIにどういうふうに関わっているかは見ています。必ずしもコントロールができるわけではないですが、SNSをやり続ける中で僕らが得ているメリットはどこなのかっていうのは常に社内で共有しているところですね。
宮永:やはり、良いコンテンツをつくればつくるほど、広告の獲得単価は自然と下がっていく傾向にあると感じています。広告のクリエイティブを改善するというよりは、アカウント全体の設計を洗練させることで、広告の効率も大きく改善されると実感しています。
青木:小手先のテクニックではなく、本質的な価値提供で好かれることが重要なんでしょうね。
「商品を勧める=相手に嫌われる」という思い込みに囚われがち
―Ciikさんは、物販で売上を立てている中で、コンテンツの中にどれくらい自社商品の販促的な内容を入れているんですか?
宮永:自社の商品のことばかり配信していたら嫌われるんじゃないかと考えていて、まさに1ヶ月くらい前に青木さんにそんな話を相談させていただいたところでした。そのときに「お客様はものを買いたい」というお話をしてくださって。それが自分の中ですごく腑に落ちたんです。それ以降は、自社商品の露出を意識的に増やすようにしました。
青木:ものを販売する仕事をしていると、「商品を勧める=相手に嫌われる」という思い込みに囚われがちですが、よく考えてみると自分が欲しい商品を教えてもらえることって嬉しいことだと思うんですよ。僕も「大人男子ラボ」を見始めた当時、どのワックスを選べばいいか迷っていて。そんなときに、「これがおすすめですよ」って言われたので、「ありがとうございます!」とすぐ買いましたし。
逆に、そのコンテンツが響かない相手であれば、そもそも対象外なのだと思います。僕のことを全然好きじゃない人に「お茶行きませんか? 」って誘って断られたら、それ以上に誘わなくてよかったってなるじゃないですか。そこはどんどん行って、離れていく人は離れてもいいんじゃないって話をしたんですよね。
宮永:その話を聞いてから吹っ切れました。実際、YouTubeの「◎◎で買えるおすすめ◎選」とかみたいな動画ってすごく伸びるんですよ。世の中の人たちはみんな買いたいものを探しているんだなって。
青木:よく考えてみたら本屋さんでお金を払って買う雑誌だって、商品の情報ばかりじゃないですか。でも雑誌は読んでおもしろくなるように編集してあって、イーコマースは買いやすさに最適化して編集しているから読んでもおもしろくない。僕らみたいにものを売っている業種も、商品名を出すか否かよりも、コンテンツとしておもしろいかどうかが重要だと思います。
―このおもしろくするところが、また難しいところだと思うのですが、宮永さんたちの中で、おもしろいコンテンツとはこういうものだと型みたいなものはあるんですか?
宮永:ある程度、おもしろくなる型は決まっていますね。例えば商品紹介をするときに、「これがおすすめですよ」より、「僕のモーニングルーティンはこれです。その中で使っている商品はこれです」というふうにしていて。そうするとその商品を欲しくないお客さんにとっては、モーニングルーティンを知れたことで良いねってなるんですよね。商品なのか、有益な情報なのか、エンタメなのか、何かしらお持ち帰りできるものがあるような設計は心がけています。
青木:なるほど。情報多重構造ですね。商品に興味がなくてもモーニングルーティンを知れるし、商品に興味がある人は商品のことも知れる。
宮永:そうですね。買いたい人にとっては、フルマックスで本望であるコンテンツなので即買いにつながりやすい。
去年、初めてアパレルの販売をしたのですが、その1発目がハーフパンツでした。「暑い夏にハーフパンツを履きたいけど、少年っぽくなっちゃいません?」っていうコンテンツで。少年っぽくならない服選びとコーディネートを紹介して、その中にうちのハーフパンツを使いました。
そうしたらその動画の保存数がすごくて。保存した人の中には商品を購入していない人もいるとは思いますが、「こういうコーディネートをすればいいんだ」と学びを得たことで保存につながったのだと思います。
属人性と有益性は1:1

―続いて2つ目のテーマに移りたいと思います。CiiKさんの成功事例をお聞きできるとうれしいです。
宮永:「大人男子ラボ」の街ブラシリーズは成功事例の1つですね。原宿で大人買いをするという、ヘアスタイルも見だしなみも関係ないコンテンツですが、誰がどういうルートでどこのセレクトショップに行っていくら買い物して、どんな飲食店でどんなメニューを頼んだかを全部丸っと見せています。
この記事に限らずですが、すべてのコンテンツにおいて、属人性と有益性のバランスを1:1に保つことを意識しています。この街ブラ企画はその法則が綺麗に反映された事例だと思います。その結果、うちの世界観やお金の使い方、店のセレクトのセンスにマッチした人が興味を持ってくれ、そこから身だしなみやヘアスタイルに興味が広がり、最終的にワックスを購入してくださっているのかなと。
ただ有益情報を発信し、ユーザーを獲得するのではなくて、「大人男子ラボ」のアカウントから我々の会社を知ってもらうことも大事だと考えているので、街ブラ企画はそこのバランスが取れた成功事例になりましたね。
―逆にこれまで試した中で「これは違ったな」というような失敗事例はありますか?
宮永: 5〜6年前、D2Cという言葉が流行って、ビジネスの最先端みたいに言われていましたよね。獲得単価がいくらで、定期購入で顧客を縛って、何カ月で回収するかみたいな。その頃は我々もけっこう揺れてしまって、それが正解なんじゃないかと思って試行錯誤していました。
青木:インフルエンサーにギフティングをばら撒くのも流行っていた時代でしたよね。
宮永:そうなんです。我々も当時、インフルエンサーの方々に自社のワックスをギフティングしていたのですが、ワックスを紹介する説明を丁寧につくって送っても、ストーリーズで「Thank you!」だけで終わるみたいな(笑)。「ぐぬぬっ……」という時期もあったんですが、その失敗から得られたこともたくさんあって。
我々がコンテンツの型を大切にしているところにもつながるんですが、コンテンツに型がある人に依頼すると、すごく自然に紹介してくれるんですよね。ワックスを紹介してもらいたいなと思ってギフティングやアンケートをお願いしたいときに、日頃からヘアセットルーティンを投稿している人に絞って依頼するだけで、反応が全然違う。少なくてもいいからばら撒かず、丁寧にPRしてくれる人にだけ届けていこうと方針を変えたことで、我々のメンタルもすごく安定しましたね。
―インフルエンサーマーケティングをする上で、押さえるべき作法ってありますか?
宮永:私もインフルエンサーとしての活動をしていたことがありまして、企業様からご提供いただくこともあるんですが、インフルエンサーって自分自身をPRするのは得意なんですけど、知らない商品を紹介するのは苦手なんですよね。なので、丸投げすると全然良いものができないんです。

―企業によっては良かれと思って丸投げしているところもありそうですよね。
宮永:インフルエンサー自身に型がある方なら丸投げでも大丈夫なんですが、型のない方の場合には「この画角でこういうセルフヘアセットの動画を撮れば、コンテンツ自体が伸びやすくなります。その中でぜひ、弊社のワックスも紹介していただけないでしょうか」と、構成や型も含めてご提案することがあります。
青木:すごい! さっきからお話に型という言葉が出てきますが、そこをもう少し詳しく聞いても良いですか?
宮永:「それうま」で、男性がキッチンで独り言を言いながら料理して食べるというスタイルは、私たちが独自につくり上げた型ですが、モーニングルーティン、Get Ready With Meなど定番企画には、ある程度のフォーマットがあると思うんです。それを型と呼んでいます。「北欧、暮らしの道具店」のYouTubeもいくつか型がありますよね。
青木:僕らがYouTubeをやるときは、まず番組を開発します。それは番組を気に入ってくださった方が、まとめて見ようというモチベーションが湧きやすくなり、チャンネル登録につながりやすくなるから。
実は、ドラマの1話をYouTubeの広告に出すと視聴維持率がものすごくて。20分あるうちの9分くらい見てくれるんですよね。それだけ長く見てもらえると、Googleが高品質広告とみなしてくれるので、配信単価もグッと下げることができるんです。
宮永:もともとは芸能人のチャンネルなど別のチャンネルを見ているときに、広告の「ひとりごとエプロン」を9分間も見てしまったということですよね。
青木:広告が始まったと思わなくて見ちゃったという感じなんでしょうね。もちろん狙ってうまくいくものでもないので、簡単な話じゃないんですけど、すべてがかみ合うとそういうことが起こる。だから、やっぱり良いコンテンツをつくろうという話になるんですよね。良いコンテンツができたら、広告で第1回を見ていただく。第1回を見ていただくと、続きも見たいとなって、シリーズものだと気づくとチャンネル登録に至るみたいな。型と番組、本質は一緒のような気がしますね。
良いコンテンツが広告効果を高める
―クラシコムはWEBサイトのほかにもInstagram、LINEなど複数のチャネルを持っています。実はTikTokもやっているのですが、他のSNSに比べてあまり伸びていなくて。宮永さんはそういう伸び悩んでいるチャネルに対してどういう向き合い方をしているのでしょうか?
宮永:コンテンツづくりもものづくりなので、制作したコンテンツが届かないのは、最もつらい瞬間です。夜も眠れないほど悩むこともあります。
アカウントを立ち上げて、自信のあるコンテンツを配信して、Instagram側がどんなアカウントか理解するまでけっこう時間がかかるので、最近はInstagramのコンテンツはブースト(広告配信)して、インプレッションを増やしています。
一昔前は「フォロワーを買う」みたいな話もありましたが、フォロワーを買ってもフォロワーはコンテンツを見てくれないんですよ。インプレッションを買う場合は、実際に見た上で「良いな」と思った人がフォローしてくれるので、気に入ってくれそうな人に会いに行っているような感覚に近い。正しいセグメントでしっかりブーストして、積み上げの時間を圧縮するというのはよくやる方法です。
青木:結局、質の悪いコンテンツは、ブーストしても単価が悪いから続けられませんからね。そのコンテンツが届いてないから伸びないのか、届いても伸びないのかは早めに決着についたほうがいいから、早いうちにテストするというのは、理にかなっていますね。
宮永:本当にそう思います。あと、伸びなくなったときにアルゴリズムがどうなっているかを考える人もいると思うのですが、それも無駄だと思っていて。
SNSってアルゴリズムの変更が多いから、アルゴリズムをハックすることで伸びる人もいる。そうなると良いコンテンツかどうかは関係ないけど、アルゴリズムに振り回されてしまう。でも、良いコンテンツって昔のものでもおもしろかったりするじゃないですか。であれば、アルゴリズムに左右されず、自分たちが本当におもしろいと信じるものを丁寧につくって、確実に届けていくことに専念すべきだと考えるようになりました。
「それでも、美味いもん。」とのタイアップに関する
お問い合わせはこちら
SNSにおける属人性と再現性
―最後のテーマとなる「属人性と再現性」についてお話しいただきたいと思います。企業のSNSだと担当者が変わることで世界観が変わるというのは良くあると思うんですね。そのとき、属人性と再現性をどう担保していくかというところをお聞きしたいです。
宮永:私たちが目指しているのは箱推しです。AKB48のように入学と卒業があるような箱をつくって、新しい演者が定期的に入ることで、また盛り上がるみたいなことができないかと考えています。
登録者数万人までは宮永えいと個人のYouTubeを見ていた人からの流入が大部分でした。でも、今は私が出ていないコンテンツでも伸びるようになってきています。むしろ最近では、「それうま」に出演している加藤くんの回のほうが、私が出るよりも反応が良かったりします(笑)。そういうふうに型がちゃんとできていれば、属人性をちょっと抜いたり、同じテイストの別の演者を入れても回る状態がつくれるんじゃないかと。今後はAKB方式を検証し続けて、私がいなくても運営が回る状態を構築していきたいと考えています。

―「北欧、暮らしの道具店」も時間をかけて属人性を抜いてきているところかなと思うのですが、青木さんはどんなふうに考えていますか?
青木:属人性はパワーを持ちますよね。パワーがあるからこそ依存しすぎたときのリスクが大きくなる。でも、最初から属人性のない設計でつくろうとしても、そもそも属人性がないとメディアは立ち上がらないんですよ。なので、宮永さんたちみたいに属人で立ち上げて、時間をかけてコントロールして、リスクを軽減させていくしかないのかなと。企業担当者の方とお話をしていると、「属人性があるから、そもそも企画が通らない」という話もよく聞きます。確かに属人性はリスクがあるけど、始まらないものはリスクさえないので。属人性で立ち上げ、そこから段階的にどう抜いていくかが重要なのだと思います。
さっきおっしゃっていたように登場人物をどんどん増やしていくのは1つの手ですよね。立ち上げた人が残っているうちに登場人物を増やして、徐々に1人当たりの依存度を下げながら箱を大きくしていく。僕らも創業者の2人で始めたので、社員にどんどん出てきてもらいながら僕と店長佐藤への依存度を下げていきましたね。
参加者からの質問タイム

Q.SNSやメディア担当に必要な素養はどんなものだと思いますか?
青木:実はSNSの担当を任せるにはちょっと人事的な側面もあって。僕らの場合、YouTubeとPodcast以外のSNSは基本的に兼業です。そのスタッフの奥行きとか、才能をもっと知りたい時に任せることが多いです。SNSの適性そのものではなく、仮説検証の視点、クリエイティブな感性、論理的な思考力といった素養を重視しています。
Q.もともと身だしなみを整えるコンテンツをつくっていたところから、どうして夜ご飯を食べるというコンテンツが生まれたのかをお聞きしてもよいでしょうか?
宮永:身だしなみを整えたい層ってどんな人たちだろうって考えた時に、進んで仕事に全力で取り組んだり、自己投資意識の高い人たちなのかなと思ったんですね。で、こうした人物像が、朝起きてから寝るまでどのような行動をしているのかを想像しながら、「まだ独身の可能性が高いから、家帰って、仕事頑張った自分に『お疲れ!』って言いながらビールを飲んで、『今日も仕事終わりに良い感じの飯つくった自分かっけーじゃん』って思いたいよな」と。そんな感じで、連想しながらコンテンツが生まれています。
―おもしろいですね。でも、企業の場合、そういうふうにコンテンツの幅を広げると、「それは果たして自分たちがやるべきコンテンツなのか?」という壁にぶつかりがちですよね。「自分たちのミッションはこう」「 自分たちのブランドはこう」という枠組みを自分たちでつくってしまったりして。100%お客さんにフォーカスすることで、自ずとコンテンツも展開していけるということですね。
宮永:先ほど言ったように、自社の商品を紹介することにまだひけ目があるので(笑)。「こうしたコンテンツがあるから、自社商品を紹介しても自然だ」と捉えることで、 “言い訳”を用意している部分もあるかもしれません。言い訳があると運営している人たちのメンタル的には、少しヘルシーでいられるというのもありますね(笑)。

Q.商品購入前に関係をつくることで、信頼を獲得できるという話があったのですが、理想としているカスタマージャーニーはどんなものなのか教えていただけるとうれしいです。
宮永:カスタマージャーニーに関しては、先ほどの青木さんのご説明の通りだと思うんですけど、もちろんコンテンツだけに触れていても、買ってもらえないことは分かっているので、リアルな場に誘導することを意識しています。
たとえば、美容室で髪の毛を切ってもらうだとか、ポップアップイベントやオフ会に来ていただくとか。あとは、コンテンツといってもTikTok、Instagram、YouTubeってそれぞれ可処分時間が違うので、いかに可処分時間を長く使ってくれるYouTubeに引き込んで、そこで私たちの人柄まで知ってもらえるかという感じで、コンテンツの中でもカスタマージャーニーを描いていたりもします。
1個でも多く接点を持ってもらうことで、購買につながると考えているので、理想のカスタマージャーニーはあえて定義せず、いかに複雑に絡み合う接点を意図的に設計しています。

*
トークセッションのほか、参加者同士で感想を共有していただくお時間や登壇者も含めた懇親のお時間もご用意させていただきました。「事業を成長させるSNSマーケティング」という今回のトークを受け、皆様のお話も大変盛り上がっている様子でした。
異業種交流会やトークイベントとは、少し趣の違う本イベント。今後もさまざまなテーマ、さまざまな企業さんと共に語り合い、交流できる場を設けていければと考えています。
株式会クラシコム 代表取締役
青木耕平
2006年、実妹である佐藤友子と株式会社クラシコム共同創業。2007年より北欧ビンテージ雑貨をEC販売する「北欧、暮らしの道具店」を開業。現在は「フィットする暮らし、つくろう。」をミッションにライフカルチャープラットフォームとして、様々な商品を取り扱いながら、日々の暮らしに関するコラムや映像を制作・配信するとともに、企業へのマーケティング支援を行うなど、ライフカルチャーにまつわる事業を展開中。
株式会社CiiK 代表取締役
宮永 えいと
大人男性に向けたライフスタイルブランド「RETØUCH(レタッチ)」を展開。メンズコスメを起点に、アパレル領域にも進出し、日常に馴染む洗練されたスタイルを提案している。「大人男子ラボ」(YouTube:25万チャンネル登録、Instagram:21万フォロワー)、「それでも、美味いもん」(Instagram:20.5万フォロワー、TikTok:9.3万フォロワー)などSNSを通じて、美容・ファッション・暮らしにまつわるコンテンツを発信。コンテンツ・商品開発・リアル店舗運営を掛け合わせた独自のマーケティングを強みに、都市で生きる男性のライフスタイルを日々アップデートし続けている。
「それでも、美味いもん。」とのタイアップに興味を持たれた方はこちら
立ち上げから5ヶ月で約30万フォロワーを獲得している急成長中の料理アカウント「それでも、美味いもん。」ではタイアップパートナーになっていただける企業様を募集中です。
フォロワー属性やアカウントが支持されている理由、タイアッププランなどを記載した資料もご用意しておりますので、以下のクラシコム ブランドソリューションのお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。